講義概要
本講座では、構造化モデリング/オブジェクト指向モデリング、そして、システムモデリングについて、開発工程ごとのモデルとその表記法を習得します。講師

- 所属
- テクマトリックス(株)
- 講師名
- 牧 隆史
㈱リコーにて、事業部においてLSIの設計及び組込みソフトウェア設計(モデム、デジタルカメラなど)の設計に従事した後、研究所において要素技術開発及び社内外のモデリング教育に従事。博士(情報科学)
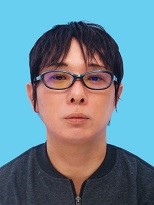
- 所属
- 株式会社SIRAS
- 講師名
- 末久 健二
開発ベンダーに勤務し、組込み系/エンプラ系の開発を経験する。 その後独立し、構造化設計を習得してからは、動くだけのコードではなく、高品質なコードを素早く開発できるようになった。開発現場での品質改善も推進している。

- 所属
- 大阪大学
- 講師名
- 春名 修介
パナソニック㈱にて、プログラミング処理系、ソフトウェア開発環境、アーキテクチャ設計手法に関する研究開発・製品応用及び社内教育に従事。現在、大阪大学大学院情報科学研究科 招聘教授。
講義内容
モデリングは、コードより抽象度が高い表記方法で、主に分析・設計内容を可視化し、システムの全体像を把握することや関係者間のコミュニケーションを図るためのツールです。これまで、モデリングの様々な記法は特定の開発方法論の中で紹介されることが多かったですが、モデリングは特定の開発手法に依存するものではなく、広くソフトウェア開発全般で利用可能です。本講義では、様々なモデリングの記法を分析・設計内容を可視化する観点で整理して、その利用局面も併せて演習することで、モデリングを身近なツールとして活用してもらうことを意図しています。
- 1.モデリングとは
- 2.構造化モデリングのモデルと表記法(イベントリスト、コンテキスト図、モジュール構造図)
- 3.オブジェクト指向モデリングで使うモデルと表記法(ユースケース図、クラス図、コンポジット構造図)
- 4.システムモデリングで使うモデルと表記法(要求図、システムコンテキスト図、内部ブロック図)
- 5.開発現場でのモデルの活用方法
- 5-1. 開発担当者としての、品質の高いソースコード開発
- 5-2. アーキテクトとしての、コミュニケーション道具
受講要件
- C言語/C++言語などでのプログラミング経験がある事。
開発現場のソースコードを改善したいという意欲があることが望ましい。
受講にあたって必要な準備
- 特にありません。
講義に関連する解説記事・参考文献・図書等
- ・SESSAME WG2(著)、「組込みソフトウェア開発のための構造化モデリング」、翔泳社
- ・SESSAME WG2(著)、「組込みソフトウェア開発のための構造化プログラミング」、翔泳社

