講義概要
設計書をどのように書けば良いか知っていますか?帳票を埋めるだけで設計したと誤解していませんか?技術は、すごい速度で進化しています。新しい技術を採用した製品開発が求められています。そういう時には、ゼロから設計書を書く必要があります。本講義では、開発プロセスの設計工程を再点検して、設計書を書く技術を学びます。講師
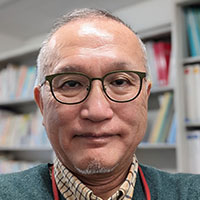
- 所属
- 名古屋大学
- 講師名
- 山本雅基
1981年日本電装(現デンソー)に入社。カーエレクトロニクス黎明期にナビゲーションシステムやエキスパートシステムなどのソフトウェアの研究・開発に従事。2004年から名古屋大学(2016年は大阪大学)。現在は、名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センターで、実践的な人材育成と企業との共同研究に従事。特任教授。
講義内容
- ・設計とは
- ・経済産業省の産業実態調査に見る他社と、自社の比較
- ・IPA/SEC(情報処理推進機構/ソフトウェア・エンジニアリング・センター)が作成したESPR(Embedded System development Process Reference)で、設計工程を学びなおす
- ・アーキテクチャ設計とは
- ・詳細設計とは
- ・設計技術
- ・RTOS(Real-Time Operating System)を知ることで設計の幅を広げる
- ・構造化,手続きの構造化,まとまりの構造化、状態遷移
- ・典型的な設計パターン
- ・ハードウェア
- ・設計TiPS
受講要件
- 特にありません。
ソフトウエアの設計経験や組込みプログラムの開発経験があることが望ましいです。
受講にあたって必要な準備
-
仕事で使用している設計書を読んで、設計書に親しんでください。
もしあれば、設計で疑問に思うことをメモしてお持ちください。当日に一緒に解決しましょう。
講義に関連する解説記事・参考文献・図書等
- IPA/SEC「改訂版 組込みソフトウェア向け開発プロセスガイド」は良書で、かつ無料でPDFが配布されています。設計に関する章が参考になります(https://www.ipa.go.jp/archive/publish/qv6pgp0000000y6r-att/000005126.pdf)

